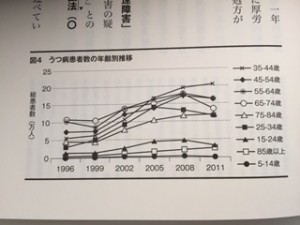今回はSRIのもたらす作用についてです。
著書『読んでやめる精神の薬』から下記抜粋します。
SRIがもたらす四つの書
人の精神活動は、必要に応じて活動させる興奮系と、それが暴走しないようにしている抑制系の絶妙なバランスで成り立っていることを、本書では何度か述べてきました。
そのバランスが崩れて興奮しすぎると、興奮毒性によって神経細胞がダメージを受け、そのダメージを受けた神経系の種類と役割に応じて、心の病気(脳の障害)が起きること、その治療には、興奮を鎮めるために休養が何よりも重要であって、神経に作用する薬剤を使うことは、かえって神経細胞の回復を阻害する可能性があることも、これまで述べた通りです。
睡眠剤・安定剤の大部分を占めるベンゾジアゼピン剤の害の具体例は、第一章と第二章で取り上げましたので、ここではSRIを中心に抗うつ剤の害について取り上げます。
SRIの害は、主に次の四つに分けることができます。
①自殺・攻撃性・暴力・犯罪などの精神症状
②胎児毒性
③新生児離脱症候群
④出血と離脱による血栓症(新生児持続性肺高血圧を含む)
このうち、もっとも大きな問題は、①の「自殺・攻撃性・暴力・犯罪などの精神症状」でしょう。SRIによる「刑罰」にともなう攻撃性や衝動性が暴力事件につながったと考えられる例は、欧米ではすでに二〇年以上前から問題になっています。
たとえば、二〇〇二年一〇月には、英国の公共放送であるBBCが、パロキセチン(商品名・パキシル)の害について、三回にわたって取り上げ、大きな反響を呼びました。
私が発行人を務める医薬品情報誌『薬のチェックは命のチェック』では、〇四年に特集で取り上げ、警告しました。
日本でも、同様の害が相次いだため、厚生労働省は〇九年にようやく警告を発し、マスメディアでも大きく取り上げられました。次項ではそうした例を紹介し、SRIの害、特に「自殺・攻撃性・暴力・犯罪などの精神症状」について考えてみましょう。
SRIによる攻撃性と暴力行為の例
SRIによる攻撃性を示す事例をいくつか紹介しましょう。まずは海外での例です。
一九八九年、ジョセフ・ウェスベッカーは米国ケンタッキー州の自分の職場において、八人を射殺し、二一人を負傷させ、自殺しました。この殺傷事件を起こす前に、SRIの一つであるフルオキセチン(商品名・プロザック、日本では未発売)を四週間ほど使用していたため、フルオキセチンのメーカー(当時リリー社、現イーライ・リリー)が提訴されました。九四年に和解が成立しましたが、その過程で企業が保有していた刺激症状に関する大量の資料が公表され、抗うつ剤使用と暴力行為との関連の可能性が大きく示唆されることになった事例です。
もう一人、六〇歳の米国人男性D・Sさんの例も見てみましょう。
過去に五回、不安とうつ病のエピソードを経験したことがありましたが、自殺や攻撃性などは経験したことはありませんでした。九〇年、うつ病に処方されたフルオキセチン服用後、興奮し、幻覚を見るような症状が三週間ほど続いた後、イミプラミン(日本での商品名・トフラニール、イミドールなど、三環系抗うつ剤)に変更して、いったんは改善しました。
しかし、九八年に別の医師が処方したパロキセチン(日本での商品名・パキシル)二〇㎎を服用して二日後、妻や娘、孫娘を射殺し、自殺しました。生存した娘婿が提訴した米国ワイオミングでの裁判で、陪審員によって、パロキセチンが人によっては殺人や自殺を起こし得る、と判定されました。そして、この事件に対して、「製薬企業(パキシルを製造販売したグラクソスミスクライン:CSK)には八〇%の責任がある」とみなされました。
この裁判の経過中に出てきた証拠資料の中には、重篤な攻撃性を示した八〇人の症例中二五人が殺人であったとのメーカーの未公表調査結果が含まれていたのです。
続いて、私が鑑定を依頼された日本での実例です。いずれもパキシルが用いられていました。
五七歳の公務員の男性は、普段はおとなしくて目立たないタイプでしたが、パキシルの服用で衝動的な行動を取るようになりました。パキシル増量後に、数百万円の公金の入った他部署の手提げ金庫を役所に置いておくのは危ないと考えて、自宅に持ち帰る、という専件を起こしています。
また、慢性疼痛症候群(医師による診断名は「線維筋痛症」)の典型的な経過にともなう反応性抑うつ状態となった三四歳の女性は、パキシルを最初に一〇㎎七日分の処方を受け、次いで二〇㎎を一〇日分、引き続き三〇㎎を二日分処方されるという具合に、徐々に用量が増えていきました。
ところが、三〇㎎一一日分のパキシルを服用しきった後、なぜか受診しなかったために、パキシルの中断状態になってしまいました。中断したと思われる日から数日後に自殺を図りました。幸い、命に別状はありませんでしたが、その三日後に受診したところ、パキシルがいきなり四〇㎎で再開されたのです。その六日後に、幼い息子を絞殺しました。
この女性の場合、中断して一週間以内に自殺未遂を起こしていました。このように、中断後に起こりやすい「自殺未遂」という重大な害反応が起きているのですから、パキシル再開後にはまた重大なことが起きる可能性が高く、本来は再開してはいけないのです。
また、仮に、再開という主治医の判断に百歩譲ったとしても、初めて服用するときと同じように、一〇㎎から再開しなければいけません。そして、徐々に増量しなければいけません。パキシルを中断して一週間以上も経過すると、血液中にはパキシルはもう残っていないからです。
担当医は精神科医でしたが、自分が処方する薬剤に関して、開始時の漸増法は知っていても、なぜそうしなければいけないのか、という理由についての理解がまるでなかったのではないかと疑います。
中断で自殺未遂を起こしていたことへの配慮もまったくなく、しかも中断後一週間以上経過しているのに、四〇㎎もの最大量で再開するというとんでもない処方でした。海外の裁判例を見れば、この女性の息子の死亡は、八〇%はパキシルのメーカーに責任があり、残りはそれを処方した医師に責任があるといっても過言ではないでしょう。
しかし、この事件では、こうした点はまったく考慮されないままに、女性の有罪判決が確定しました。
以上、抜粋終わり
上記のことを理解した上で、
あなたはSRIを服用するのかどうか再検討してください。